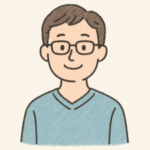作ったゲームを安全に公開する方法 – Scratch編

お子さんがScratchで一生懸命作ったゲーム、「みんなに見てもらいたい!」と目を輝かせて言われたとき、親として嬉しい反面、インターネットでの公開って大丈夫かな?と心配になりますよね。
実は、適切な準備さえすれば、子どもの作品を安全に世界と共有することは十分可能なんです。この記事では、そのための具体的な方法を、親子で取り組める形でお伝えします。
夢の実現を応援しながら、同時に安全を確保する。一見難しそうですが、段階を踏めば必ずできます。最初の小さな失敗も、大きな学びの一歩。恐れることなく、一緒に進んでいきましょう。
Scratchって何?基本を知ろう
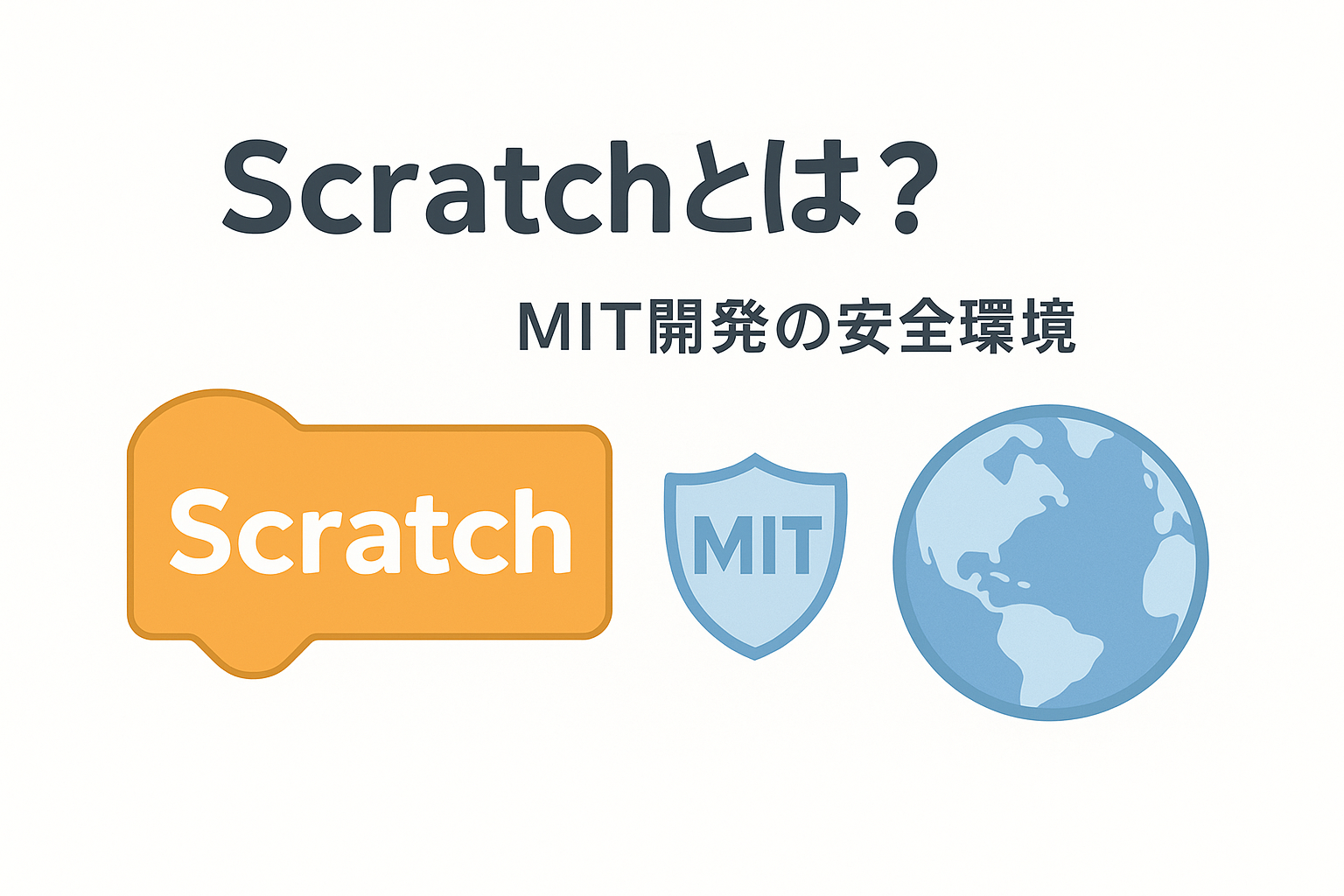
Scratchの特徴と安全性
Scratchは、MIT(マサチューセッツ工科大学)が開発した、子ども向けのプログラミング環境です。ブロックを組み合わせるだけでゲームやアニメーションが作れるため、世界中で愛用されています。
特に注目すべきは、その安全性への配慮です。開発段階から「子どもが安全に学べる環境」を最優先に設計されており、以下のような特徴があります:
- 年齢別の自動制限機能:13歳未満は自動的に制限付きアカウントになります
- 24時間体制の監視:不適切なコンテンツは迅速に対応されます
- 建設的なコミュニティ文化:お互いを尊重し、学び合う雰囲気が根付いています
なぜ公開することが大切なのか
「わざわざ公開しなくても…」と思われるかもしれませんが、作品を共有することには大きな意味があります。
創作意欲の向上 他の人からの「いいね!」や建設的なコメントは、子どもの創作意欲を大きく刺激します。「次はもっと面白いものを作ろう」という前向きな気持ちが生まれるんです。
技術的な成長 他の作品を見ることで、「こんな表現方法があるんだ」「この仕組みを真似してみよう」と、自然に技術力が向上します。
コミュニケーション能力の発達 作品の説明を書いたり、コメントに返事をしたりすることで、自分の考えを言葉にする力が育ちます。
不安や心配があるのは当然です。でも、適切な準備をすれば、これらの恩恵を安全に受けることができるんです。

公開前の準備:安全設定の確認

アカウント設定の基本
まず最初に、Scratchアカウントの設定を確認しましょう。特に重要なのは以下の項目です:
プロフィール設定
- ユーザー名:本名ではなく、ニックネームを使用
- 自己紹介:趣味や興味を中心に、個人を特定できる情報は避ける
- プロフィール画像:オリジナルのイラストや、個人が特定できない画像を選択
例えば、「田中太郎」という名前なら、「GameMaker_T」や「Creative_Kid123」といった感じのユーザー名がおすすめです。
プライバシー設定
- コメント機能:最初は「フォロワーのみ」に設定
- プロジェクトの公開範囲:段階的に拡大していく設定
- メッセージ機能:必要に応じて制限をかける
個人情報の取り扱い
これは本当に重要なポイントです。以下の情報は絶対に公開しないよう、お子さんと一緒に確認してください:
絶対にNGな情報
- 本名(姓名)
- 学校名
- 住所や最寄り駅
- 電話番号
- 家族の情報
注意が必要な情報
- 作品に写り込んだ地域の特徴的な建物
- 制服や校章が写った写真
- 方言や地域特有の表現(特定されるリスクがある場合)
子どもたちには「インターネットは世界中の人が見ている」ということを、恐怖心ではなく、ワクワクする事実として伝えましょう。「アメリカの子どもも、ブラジルの子どもも君の作品を見るかもしれないよ」と話すと、多くの子どもが目を輝かせます。
その上で、「だからこそ、自分や家族の安全を守る情報は秘密にしておこうね」と説明すれば、理解してもらえるはずです。
段階的公開戦略:家族から世界へ

第1段階:家族・友人限定公開
最初は身近な人だけに見てもらう「練習期間」から始めましょう。
設定方法
- プロジェクトを作成後、「公開しない」に設定
- 特定の人にだけリンクを共有
- フィードバックを受けて改善
この段階で確認すること
- 作品が意図通りに動作するか
- 説明文は分かりやすいか
- 不適切な内容が含まれていないか
おじいちゃんおばあちゃんに見せて喜んでもらえたら、お子さんの自信にもつながりますね。
第2段階:学校・地域コミュニティでの共有
家族からの反応が良好だったら、次は学校の友達や地域のプログラミング教室で共有してみましょう。
具体的な方法
- 学校の授業での発表
- 地域のプログラミング教室での作品展示
- 友達同士での作品交換
この段階では、同世代からのリアルな反応を得ることができます。「ここが面白い」「ここが分からない」といった率直な意見は、とても貴重です。
第3段階:Scratchコミュニティでの限定公開
いよいよScratchの世界デビューです。でも、最初は「探しにくい場所」での公開から始めましょう。
設定のコツ
- タイトルにはメインキーワードを避ける
- 説明文は最小限に
- 「未完成」や「テスト版」といった表記を入れる
これにより、偶然見つけてくれた人からの優しいフィードバックを受けながら、大きな注目を浴びる前に改善できます。
第4段階:一般公開とフィードバック収集
準備が整ったら、いよいよ本格的な公開です。
成功のポイント
- 魅力的なタイトルとサムネイル
- 遊び方の分かりやすい説明
- 制作過程や工夫した点の紹介
- 他の作品へのリスペクトを示すコメント
この段階まで来ると、お子さんの作品に対する自信も十分に育っているはずです。
どの段階でも、「失敗は成功への階段」だということを忘れないでください。思うような反応が得られなくても、それは次の作品をより良くするための貴重な学びです。
著作権の基本:安心して使える素材選び

Scratchで安全に使える素材
著作権って難しそうに聞こえますが、基本を押さえれば怖くありません。Scratchの場合、特に安心なのは以下の素材です:
Scratch内蔵の素材
- キャラクター(スプライト)
- 背景
- 音楽・効果音
これらはすべて、商用利用も含めて自由に使うことができます。MITが権利をクリアした上で提供しているからです。
自作素材
- 自分で描いたイラスト
- 自分で録音した音声
- 自分で撮影した写真(個人情報に注意)
自作の素材なら、著作権は100%自分にあります。ただし、写真の場合は背景に他人の家や車が写り込まないよう注意しましょう。
注意が必要な素材
既存のキャラクター ポケモンやディズニーキャラクターなど、有名なキャラクターの使用は避けましょう。ファンアートとして個人で楽しむ分には問題ありませんが、公開する場合はリスクがあります。
市販の音楽 CDや配信で販売されている音楽の使用は避けましょう。「好きな曲だから」という理由だけでは使用できません。
インターネットから拾った画像 検索して見つけた画像は、多くの場合著作権があります。「フリー素材」と書かれていても、利用条件を確認することが大切です。
クリエイティブ・コモンズの活用
どうしても外部の素材を使いたい場合は、「クリエイティブ・コモンズ」ライセンスの素材を探してみましょう。
利用可能なサイト
- Freesound(効果音)
- Pixabay(画像)
- Wikimedia Commons(画像・音声)
これらのサイトでは、作者の名前を表示することで自由に使える素材が多数公開されています。
著作権は「クリエイターの権利を守る仕組み」です。お子さんにも、「自分の作品を大切にしてもらいたいように、他の人の作品も大切にしよう」と伝えることで、自然に理解してもらえるでしょう。
保護者ができるサポート

公開前のチェックリスト
お子さんが「公開したい!」と言ってきたら、一緒にこのチェックリストを確認してみてください:
安全性チェック
- [ ] 個人情報は含まれていないか
- [ ] 家族の写真や名前は写っていないか
- [ ] 学校や地域が特定できる要素はないか
- [ ] 不適切な言葉や表現は使われていないか
技術的チェック
- [ ] ゲームは最後まで遊べるか
- [ ] 説明文は分かりやすいか
- [ ] 操作方法は明記されているか
- [ ] エラーで止まることはないか
著作権チェック
- [ ] 使用している素材は問題ないか
- [ ] 外部素材を使う場合、出典は明記されているか
- [ ] 既存キャラクターは使用していないか
継続的なサポート方法
公開後も、定期的にお子さんの活動をサポートしましょう。
週1回の振り返り
- どんなコメントがついたか
- 新しい発見や学びはあったか
- 困ったことや悩みはないか
- 次に作りたいものはあるか
この振り返りの時間は、親子のコミュニケーションを深める貴重な機会でもあります。
成長を記録する
- 作品の進歩を写真に残す
- 受けたコメントの中で特に嬉しかったものを記録
- 新しく覚えた技術をメモする
- 挑戦したいことをリストアップ
子どもとの対話のコツ
褒めるポイント
- 完成度よりも挑戦する姿勢
- 他の人への優しいコメント
- 困難に立ち向かう粘り強さ
- 創意工夫や独創性
避けるべき言葉
- 「他の子と比べて…」
- 「もっと上手に…」
- 「時間の無駄」
- 「子どもの遊び」
代わりに、「どこを工夫したの?」「次はどんなことに挑戦したい?」「どんな気持ちで作ったの?」といった、子どもの想いや過程に注目した質問をしてみてください。
より、挑戦をさせてあげいた!と思ったときにオススメなのが、
子ども向けプログラミング・ロボット教室【LITALICOワンダー】
一斉授業のプログラミングスクールとは異なり。
- 1対1−4名の少人数制授業
- 個性にあわせたオーダーメイドカリキュラム
- 作りたいものを自分で決める
オンラインレッスンもあります。
運営会社のLITALICOは、発達障害などの福祉・教育領域で事業展開をする会社。発達支援に関するノウハウが多くあるため、オーダーメイドカリキュラムに強みがあるんです。
なので、あなたのお子さんにあわせたレッスンが受けられるんですね。
これなら、子供もより熱中しそう!
デジタル時代の子育ては確かに新しい挑戦ですが、基本は変わりません。愛情と関心を持って見守ることが、何よりも大切なサポートなのです。

トラブル対応:もしもの時の対処法
よくあるトラブルと対処法
どんなに注意していても、時にはトラブルが起こることがあります。でも、適切に対処すれば大きな問題になることはありません。
不適切なコメントを受けた場合
即座に行うこと
- そのコメントをスクリーンショットで保存
- Scratchの報告機能を使用
- 必要に応じてそのユーザーをブロック
- お子さんと一緒に状況を整理
お子さんへの声かけ 「変なコメントがあったね。でも、これはあなたの作品や人格に問題があるからではないよ。インターネットには時々、適切でない行動をする人もいるんだ。大切なのは、そういう人の言葉に惑わされないことだよ。」
作品が真似された・盗用された場合
実は、これは「人気作品の証拠」でもあります。
対処の手順
- 元の作品の公開日を確認
- 真似された作品のリンクを保存
- Scratchの報告機能で連絡
- 可能であれば、真似した人に直接コメント
教育的な対応 真似されることを完全に悪いこととして捉えるのではなく、「リスペクトを持った真似の仕方」について話し合う機会にしましょう。
緊急時の対応手順
個人情報が漏れてしまった場合
- 即座にプロジェクトを非公開に変更
- 漏れた情報の範囲を確認
- 必要に応じて学校や関係機関に相談
- 今後の対策を検討
この場合、慌てることなく冷静に対処することが重要です。多くの場合、迅速に対応すれば大きな問題にはなりません。
不適切な内容を公開してしまった場合
- すぐにプロジェクトを削除または修正
- 影響を受けた人がいれば謝罪
- なぜそうなったかを振り返る
- 再発防止策を考える
予防策の継続的な見直し
月1回の安全チェック
- アカウント設定の確認
- パスワードの強度チェック
- 公開中の作品の再確認
- フォロワーの確認
年1回の大掃除
- 古い作品の整理
- プライバシー設定の全面見直し
- 新しい安全機能の確認
- 家族でのルール更新
トラブルが起きたとき、「もうやめさせよう」と考えるのは自然な反応です。でも、実社会でも様々なトラブルがあるように、デジタル世界でも完全にリスクをゼロにすることはできません。
大切なのは、トラブルを恐れて挑戦をやめることではなく、適切な対処法を身につけて、より安全に活動を続けることです。
私自身、クラウドファンディングプロジェクトでも様々な困難がありましたが、それらを乗り越えたからこそ、今の成功があります。子どもたちにも、困難を乗り越える力を身につけてもらいたいですね。
まとめ:創作の喜びを安全に分かち合おう
これまでのポイントを振り返って
ここまで、Scratchで作ったゲームを安全に公開する方法について、詳しくお話ししてきました。要点をまとめると:
段階的なアプローチの重要性
- 家族→友人→コミュニティ→一般公開の順序
- 各段階での学びと改善
- 子どもの成長に合わせたペース調整
安全性の確保
- 個人情報の徹底的な保護
- 適切なプライバシー設定
- 継続的な監視とサポート
著作権への配慮
- 安全な素材の選択
- クリエイターへのリスペクト
- オリジナリティの重視
トラブルへの備え
- 予防策の実施
- 適切な対処法の習得
- 冷静な判断力の養成
子どもの成長への効果
適切にサポートされたデジタル創作活動は、子どもに多くの恩恵をもたらします:
技術的スキル
- プログラミング的思考の発達
- 問題解決能力の向上
- 創造性の発揮
社会的スキル
- デジタルシチズンシップの習得
- 多様な人々とのコミュニケーション
- 建設的なフィードバックの受け取り方
人格的成長
- 挑戦する勇気
- 失敗から学ぶ力
- 他者への共感と尊重
保護者として大切にしたいこと
子どもの夢を応援する姿勢 「いつか有名なゲームクリエイターになりたい」「自分の作ったゲームで人を楽しませたい」そんな子どもの夢を、まずは心から応援してあげてください。
どんなに小さな作品でも、子どもにとっては大切な表現です。その価値を認めてあげることが、何よりも重要なサポートになります。
失敗を恐れない環境づくり 「バグがあっても大丈夫」「最初は上手くいかなくても当然」「失敗も学びの一部」
そんな安心感のある環境があれば、子どもは思い切って挑戦できます。
長期的な視点での見守り デジタルスキルは一朝一夕で身につくものではありません。時には熱中し、時には飽きるかもしれません。それも自然な成長過程の一部です。
長期的な視点で、子どもの興味と成長を見守ってあげてください。
デジタル時代の子育て
私たち保護者の世代は、インターネットがない時代に子ども時代を過ごしました。だからこそ、デジタル世代の子どもたちに何をしてあげればいいか、戸惑うことも多いでしょう。
でも、基本的な子育ての原則は変わりません:
- 愛情を持って見守る
- 適切な境界を設ける
- 挑戦を応援する
- 失敗を受け入れる
- 一緒に学ぶ姿勢を持つ
地方で不動産業を営みながら、多くの家族と接してきた経験から確信を持って言えることは、子どもの可能性は私たちの想像を遥かに超えるということです。
デジタル技術も、使い方次第で子どもたちの可能性を大きく広げてくれる素晴らしい道具になります。
最後に:一歩を踏み出す勇気
もしお子さんが「Scratchで作ったゲームを公開したい」と言ってきたら、ぜひこの記事を参考に、一緒に挑戦してみてください。
最初は不安もあるでしょう。「本当に大丈夫かな」「何かトラブルが起きたらどうしよう」そんな心配も当然です。
でも、適切な準備と継続的なサポートがあれば、その心配は大きな喜びに変わります。子どもが初めて他の人からの「いいね!」をもらったときの表情。自分の作品について嬉しそうに説明する姿。新しい技術に挑戦する意欲的な姿勢。
そんな瞬間に出会えることを、心から願っています。
子どもたちの創作活動は、未来への投資でもあります。今日の小さな一歩が、明日の大きな成長につながる。そのお手伝いができれば、こんなに嬉しいことはありません。
安全で楽しいデジタル創作ライフを、親子で一緒に楽しんでくださいね。